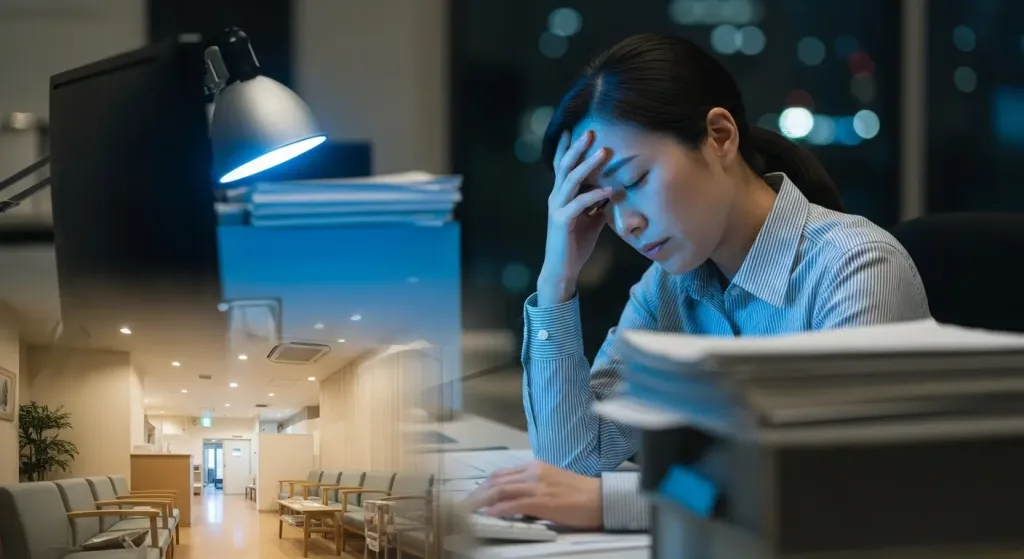
目次
はじめに
その「限界サイン」、放っておかないで 朝、目覚ましを止めたまま体が動かない。メールを見るだけで胸がザワつく。週末に寝ても疲れが取れない。そんなサインが続くとき、あなたの心と体は「助けて」と静かにSOSを出しています。心療内科は、仕事のストレスで揺らいだ心身のバランスを取り戻すための実用的な拠点です。早めに相談することで、短い治療で回復することも少なくありません。
受診の目安:こんなときは心療内科を
- 2週間以上、眠れない・食欲がない・ぼんやりする・涙もろい・焦りが強い
- 仕事に行くと動悸や吐き気、腹痛・頭痛が出る(内科で異常がないと言われた)
- 受け流せていた業務や人間関係に耐えられない、ミスが急に増えた
- 「消えてしまいたい」とよぎる(緊急性が高いサイン。迷わず受診・相談を)
- 長時間労働や人員不足、ハラスメント、評価不安が慢性的にある
心療内科でできること
- 評価と診断:気分・不安・睡眠・身体症状、職場環境、人間関係、生活リズムを丁寧に聴取
- カウンセリング(認知行動療法、ストレス対処トレーニング、マインドフルネス)
- 薬物療法(必要最小限。副作用と効果を見ながら調整)
- 休職・復職サポート(診断書、産業医・人事との連携、段階的な復職プラン)
- 仕事と生活の調整(業務量の見直し、通勤時間、在宅・時短の検討)
- 睡眠・運動・栄養の支援(睡眠衛生、運動習慣の導入など)
よくある病名と症状の特徴
- 適応障害:特定のストレス(部署異動、上司交代など)に反応して不眠・不安・抑うつが出る。ストレスから距離を置くと改善しやすい。
- うつ病:興味や喜びの喪失、強い疲労感、自己否定、決断困難、朝方に悪化しやすい。不眠や食欲低下を伴うことが多い。
- 不安障害(パニック症など):動悸・息苦しさ・めまいの発作、予期不安で外出や通勤が怖くなる。
- 不眠症:寝つけない、途中で目覚める、早朝覚醒。日中の集中力低下・イライラをともなう。
- バーンアウト(燃え尽き症候群):情緒的消耗感、脱人格化(割り切り・投げやり)、有能感の低下。診断名ではないが臨床で多い。
治療の進め方(エビデンスに基づく要点)
- 認知行動療法(CBT)とマインドフルネス:ストレス反応のメカニズムを学び、考え方と行動を少しずつ変える。マインドフルネスは不安・抑うつの軽減に有効性が示されています。[Goyal 2014, JAMA Intern Med]
- 睡眠には認知行動療法的介入:認知行動療法的対処は眠りの質と日中機能を改善します。[Trauer 2015, Ann Intern Med]
- 薬物療法:中等度以上のうつ・不安では抗うつ薬が奏功することが多い。副作用や職務への影響を話し合いながら最小有効量で開始し段階的に。薬だけに頼らず心理療法と併用を推奨。[Cipriani 2018, Lancet]
- 協働ケア(Collaborative Care):主治医・心理職・職場と連携する体制は回復率を高め、再燃を減らします。[Archer 2012, Cochrane]
- 職場ストレスの整理:仕事の要求度が高く裁量が低い環境や、努力と報酬の不均衡は、抑うつリスクを高めます。構造的な見直しが必要な場合は産業医や人事と協働します。[Stansfeld & Candy 2006; Nyberg 2013]
- バーンアウト対応:休息と役割調整、価値観の再確認、対人支援の強化が中核。漫然と我慢するより早期介入が回復を早めます。[Maslach & Leiter 2016]
体験談(仮名・一部要約)
- 事例1:佐藤さん(30代・事務職) 繁忙期から不眠と腹痛が続き、朝が動けなくなって受診。適応障害の診断で2週間の休養とCBTを開始。睡眠衛生と業務の優先順位づけを練習し、4週で短時間勤務から復帰。6カ月後も再燃なく勤務継続。「休む決断が怖かったけど、短く集中して整える方が結局は早かった」とのこと。
- 事例2:田中さん(40代・管理職) 部下育成と評価プレッシャーでイライラと空虚感が増え、ミスも増加。バーンアウト傾向と不眠症。マインドフルネスの短期プログラムと不眠対策、必要最小限の薬を併用。チーム内でタスク分散と会議時間の上限を設定。3カ月で「人に任せる技術」を体得。「頑張り方を変える」ことで回復。
よくある質問(Q&A)
Q1:いつ受診すべきですか? A:不調が2週間以上続く、仕事に行けないほど辛い、希死念慮がよぎる場合はすぐに。悪化する前の相談が最短の回復ルートです。
Q2:受診したら必ず薬が出ますか? A:いいえ。非薬物療法が第一選択になることも多いです。症状の強さや生活・仕事の状況に合わせて一緒に決めます。
Q3:会社に知られますか?診断書は必要? A:医療情報は守秘義務で守られます。勤務調整や休職が必要な場合のみ、内容を最小限にして診断書を発行します。
Q4:休んだら復職が不安です。 A:段階的復帰(短時間→通常勤務)で再燃を防ぎます。産業医・人事と連携して具体的な復職計画を作ります。
Q5:カウンセリングはどのくらい通いますか? A:目安は2〜8回(週1〜隔週)。不眠や不安などテーマにより調整します。
Q6:オンライン診療は可能? A:初診は対面を基本としつつ、再診やカウンセリング一部はオンライン対応が可能な医療機関もあります。各院の方針をご確認ください。
受診前に今日からできるセルフケア
- 睡眠を固定:起床時刻を毎日同じにし、夜は布団でのみ寝る。寝る前1時間は画面オフ。
- 体を少し動かす:10分の速歩でもOK。昼の光を浴びる。
- 言語化する:不調の時間帯・きっかけ・体のサインを書き出す。診察が効率的に。
- 「今できる最小の一歩」を決める:メールは3本だけ返す、会議は15分短縮を提案する等。
- 相談先を保存:かかりつけ候補の心療内科、産業医、社内EAP、地域の相談窓口。
医師からのメッセージ
心は折れない代わりに、静かに摩耗します。限界まで耐えることは美徳ではありません。あなたの仕事と人生を長く守るために、「今は整えるとき」と決めてください。心療内科は弱さの証明書を出す場所ではなく、回復と再出発の支援拠点です。ひとりで抱え込まず、一緒に作戦会議をしましょう。
参考文献(PubMed)
- Stansfeld S, Candy B. Psychosocial work environment and mental health—a meta-analytic review. Psychol Med. 2006;36(7):926-939. PMID: 16403298. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16403298/
- Nyberg ST, et al. Job strain as a risk factor for severe depressive symptoms: multicohort study with meta-analysis. BMJ. 2013;346:f3073. PMID: 23704745. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23704745/
- Maslach C, Leiter MP. Understanding the burnout experience. World Psychiatry. 2016;15(2):103-111. PMID: 27265691. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27265691/
- Goyal M, et al. Meditation programs for psychological stress and well-being: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2014;174(3):357-368. PMID: 24395196. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24395196/
- Trauer JM, et al. Cognitive Behavioral Therapy for Chronic Insomnia: A systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2015;163(3):191-204. PMID: 26237785. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26237785/
- Cipriani A, et al. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs. Lancet. 2018;391(10128):1357-1366. PMID: 29477251. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29477251/
- Archer J, et al. Collaborative care for depression and anxiety problems. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(10):CD006525. PMID: 22696341. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22696341/
- Richardson KM, Rothstein HR. Effects of occupational stress management intervention programs. J Occup Health Psychol. 2008;13(1):69-93. PMID: 18457483. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18457483/

